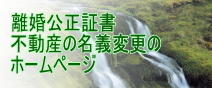Q&A - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所
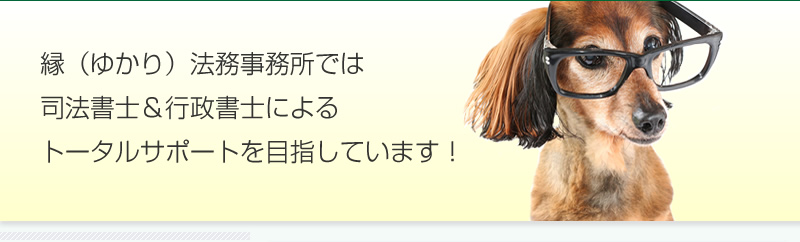
Q&A
遺言Q&A/相続Q&A/相続登記Q&A/成年後見Q&A/
任意整理Q&A/自己破産Q&A/過払いQ&A/個人再生Q&A/
離婚協議書Q&A/離婚公正証書Q&A
| 遺言できる人はだれ? |
- 満15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法961)とされています。
- 2人以上が同一の証書で遺言をすることはできません。
- 成年被後見人である場合、遺言の制限がございます。
- 認知症等(意思能力がない)の場合は基本的に遺言はできません。
(医師の診断等で意思能力に問題ないことの証明がされれば可能です)
| 遺言の種類はどういうがあるの? |
普通方式と特別方式がございます。特別方式は、遺言者の死亡が危急に迫っている場合や、一般社会と隔絶した場所にあたる場所にあるため普通方式によることができないときに、特に要件を緩和して認められる方式です。一般的に「遺言」として言われているものは、普通方式になります。
| 複数の遺言がある場合どうなるの? |
作成時期の異なる複数の遺言がある場合、お互いに内容が抵触する部分については、
最後のものが有効な遺言となります。
| 検認とはなんですか? |
公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。これは封のしてある遺言を裁判所で開封することによりそれ以降の変造を防止する効果があります。登記に使用する場合は検認がないと申請できません。
| 誤って開封してしまったらどうしたらいいの? |
開封後であっても検認はできますので、すぐに検認してもらいましょう。 検認は遺言の有効、無効を判断するものではないため、「検認が無いため遺言書が無効」となる訳ではありません。しかし開封後に何か手を加えたのでは、と疑いをかけられる恐れもあるので未開封で検認することが望ましいです。
| 証人となれる人はどんな人なの? |
証人とは、未成年者、成年被後見人、遺言者の親族(4親等内)、推定相続人や受遺者(配偶者、直系血族を含む)、公証人の関係者(書記等)はなることができません。 証人がいない場合は当事務所で証人を用意しますのでご安心ください。
| 遺言執行者とはどういう人なの? |
遺言書に書かれている内容を実現するために、遺言を執行する権利を持つ人のこと です。そして遺言執行者のみが、認知及び推定相続人の廃除又は廃除の取り消しの手続きができます。ゆえに上記の事項を遺言書に記載される場合は遺言書で指名しておくほうが望ましいかもしれません。指名されていなくても、後から裁判所に選任してもらうこともできます。遺言執行者は、未成年者および破産者を除いて、誰でもなることができます。 遺言執行者を選任しておくと相続自体がスムーズに進むこともあります。ご気軽にお問い合わせください。
| 遺言書の方式のうちどれが一番よいのですか? |
やはり公正証書遺言が一番安心でしょう。検認の必要もなく、内容も無効となる危険が少ないためです。
| 一度作成した遺言書を変更することはできますか? |
もちろん変更することができます。しかし公正証書遺言の場合は再度費用がかかります。
▲このページの上へ
| 法定相続って何なの? |
| 相続税はいくらからかかるの? |
遺産総額が5000万円+(相続人×1000万円)の額以内ならば相続税はかかりません。(基礎控除) 基礎控除以内の場合は申告の必要はありません。
| 相続税の基礎控除以外には軽減措置はないの? |
小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減等があります。小規模宅地の評価減とは、 居住用の自宅や事業に使用している土地は最大80%まで評価を減額するものです(面積等に条件あり)。配偶者の税額措置とは、配偶者の相続分が基礎控除分以下か、それを超えても相続した財産の総額が1億6000万円までは課税対象にならないというものです。この制度を使う場合は相続税の申告が必要です。
(相続開始から1 0か月以内)
| 相続人すべての意思確認はするの? |
遺産分割協議の場合、利益を得る場合も不利益になる場合も相続人全員の意思を確認しなければなりません。勝手に登記をしてしまうと後で争いになる場合や無効に なる場合もあるからです。
| 相続人が未成年の場合は何か手続きが必要なの? |
相続人が未成年の場合で、遺産分割協議をする場合は特別代理人を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。法定相続の場合は必要ありません。当事務所で 選任の書類を作成することもできます。
| 相続人が行方不明の場合はどうするの? |
行方不明の期間により手続きが変わることもありますが不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。
▲このページの上へ
| 相続登記はしなければいけないの? |
相続登記はいつまでにしなければいけないという期間はありません。 しかしそのままにしておくとその相続人が亡くなった場合等に誰が相続人になるかなど複雑になってしまう可能性や他の相続人の債権者が代位により相続登記を行い持分を差し押さえてしまう危険性もあります。また必要書類となる住民票の除票は5年で無くなってしまうので他の書面が必要な場合があります。なるべく早いうちに手続きすることをお勧めします。
| 登記を申請するにあたり何か自分ですることがあるの? |
法務局の提出は当事務所で行います。書類の取り寄せも当事務所にご依頼の場合は当事者の方には書類へのご署名、ご押印をしていただく程度です。遺産分割協議書を作成する場合は印鑑証明書が必要となりますので印鑑証明書はご取得をお願い致します。
| 相続登記は全国でできるの? |
はい、不動産の所在地管轄の法務局に対する申請は全国対応できます。平成20年度より登記済権利証の郵送返却も可能となりましたので他の事務所にお願いすることなく当事務所のみで手続きを完了させることができます。
| 相続登記はどのぐらいで終わるの? |
書類がそろっていれば法務局に申請して平均1〜2週間で終わります。
| 相続登記の費用はどのくらいなの? |
まず登録免許税(税金)として固定資産税評価額の1000分の4かかります。報酬としては土地建物の評価額、書類の取り寄せ、作成等で変わってきますが平均すると3万円〜10万円ぐらいです。その他に実費、消費税がかかります。
▲このページの上へ
| 成年後見の申立てのみの依頼はできますか? |
はい。後見人が決まっている場合(親族等)申立てのみのサポートをさせていただきます。
| 相談は料金がかかるの? |
初回のご相談は無料とさせていただきます。2回目からは1時間5000円でお願い致します。
| 成年後見、保佐、補助の違いはなんですか? |
補助の場合は本人の同意が必要となります。成年後見か保佐のどちらかは最終的には裁判所が判断します。保佐で申立てをしても成年後見が妥当な場合は成年後見しか認められません。
| 成年後見は申立てをしてからどの位期間がかかるの? |
裁判所の審理期間については、個々の事案により異なるため一概にはいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査等個々の事案により異なるためです。多くの場合4か月以内となっています。
| 不動産売却で売主が認知症の場合はどうすればいいの? |
認知症の程度により異なりますが不動産の売却について判断できない場合は成年後見、保佐の申立てが必要となります。申立てをせずにそのまま売却してしますと意思能力のない売買ということで無効となってしまう可能性があります。無効の場合第三者に売却していても元の所有者に戻さねばなりません。ゆえに、売主、買主ともに重要なことといえます。
▲このページの上へ
| 成功報酬、減額報酬なしとはどういうことですか? |
成功報酬とは、着手金のほかに債権者との和解が決まったら1社につきいただく報酬のことです。(事務所によって違いますが2万円ぐらいが平均みたいです)
減額報酬とは、例えば、債権額の総額400万円が交渉後200万円になった場合減額された200万円の10%(事務所によって違います)の20万円が報酬に加わります。
結局、お客様が支払う金額が最後まで確定しないのと費用が高額になってしまう可能性があるため当事務所では成功報酬、減額報酬はいただきません。
| 面談のときに持っていくものは何ですか? |
債権者との契約書及び返済の領収書等の契約の内容がわかるもの、身分証明書、認印等、詳しいことはご連絡ください。
| 任意整理をするとどのくらい借金が減るのですか? |
取引が長いほど債権額が減ります。しかし借入れの利率が利息制限法(18%・借りている金額によって違います)よりも低い場合は減額は見込めないでしょう。
| だれにも知られずにすることはできますか? |
代理人として債権者と交渉するためだれにも知られずに任意整理をすることができます。
| 保証人がついている場合も任意整理できますか? |
保証人がついている場合は請求が保証人にいってしまいます。保証人の方も一緒に任意整理をすれば請求はストップします。
| 司法書士と弁護士で違いがあるのですか? |
任意整理においては、ほとんど違いはありません。司法書士と弁護士で違った結果がでることはないと思います。司法書士か弁護士のような資格で判断するのではなくその担当者で判断したほうが望ましいと思います。
| 期間はどのくらいかかるのですか? |
まず、受任通知を発送し、取引履歴を開示してもらいます。それから和解交渉となりますので平均すると3ヶ月から6ヶ月ぐらいだと思います。
| 過払い金がある場合はどうなるのですか? |
過払い金がある場合は、もちろん返還交渉いたします。安易な和解をせず、できる限り返還させます。
▲このページの上へ
| 自己破産できない人とはどういう人ですか? (免責不許可事由) |
- いくつかありますが代表的なものは次のようなものです。
- ・ 過去7年以内に破産による免責をうけていないこと
- ・ 借金の理由が浪費やギャンブルではないこと
- ・ 財産を隠していたり、嘘をついたりしたこと
| 面談のときに持っていくものは何ですか? |
債権者との契約書及び返済の領収書等の契約の内容がわかるもの、身分証明書、認印等、詳しいことはご連絡ください。
| 家族や勤務先に内緒ですることができますか? |
| 自己破産するとブラックリストに載るのですか? |
ブラックリストというものは存在しないのですが、信用情報機関といわれているものに事故情報として登録されます。5年から7年はローン等はできなくなります。
| ほかに不都合なことがありますか? |
| 過払い請求のみの依頼はできるの? |
| 事故情報(ブラックリスト)に載るの? |
| どのくらいの期間がかかるの? |
![]()
| 消費者金融のみしか過払いは発生しないの? |
![]()
| 自己破産の場合は過払い金の請求はできないの? |
![]()
| 司法書士と弁護士で違いがあるのですか? |
| 消費者金融のみ過払い請求することはできるの? |
| 個人で行うことはできないの? |
| 住宅ローンも減額することができますか? |
| 住宅ローン特則とはなんですか? |
住宅ローン特則とは、裁判所が強制的に住宅ローンの返済計画の引き直しを行う制度です。毎月の支払い金額を少なくしたり、支払い期限をのばしたりします。
ただ、住宅ローンの残金は減額されません。また建物に住宅ローンの抵当権が設定されていることが必要となり、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は利用できません。
抵当権が実行されて家を失うのを防ぐ制度のためです。
| 誰でも個人民事再生を利用できるのですか? |
| 小規模個人再生と給与所得者再生の違いは? |
次に、小規模個人再生は債権者、債権総額の半数の同意が必要となります。給与所得者再生はその同意が不要となります。
▲このページの上へ
| 離婚の種類について? |
調停離婚等の裁判所への提出書のみの業務はできますが、代理人となれるのは弁護士のみのため争いのあるものはご遠慮いただいています。
| 弁護士、司法書士、行政書士の違いは? |
弁護士は代理人になれます。本人に代わりに相手と交渉することができます。
行政書士は争いのない部分で協議書の作成や公正証書の代行ができますが不動産の移転の登記はできません。
司法書士は裁判書類の作成はできますが代理人にはなれませんし、不動産の移転のない協議書の作成もできません。しかし、不動産の移転については代理することができます。
当事務所は、司法書士、行政書士事務所のため公正証書の代行がら不動産の移転までサポートすることができます。
| 協議書は作成しなくていけないの? |
のちのちの争いを防止するために作成しておいたほうが安心だと思います。
| 無料の相談は行っていますか? |
面談、電話での相談は、1時間5250円となっております。
ご依頼をいただいた場合は相談料はかかりません。
| 自分で作成しても良いものなの? |
ただし、内容に不備がある場合にはその効力がなくなる可能性もありますのでご注意しくください。
▲このページの上へ
| 全国対応していますか? |
| 電話のみで依頼はできますか? |
不動産がある場合には、本人確認が必要となるため面談が必要となります。また、内容の確認やアドバイス等、電話だと難しい部分があるので面談をお願いしています。
| 公証役場には出向かなくてはならないのですか? |
| 不動産の登記はすぐにしなくてはいけないのですか? |
▲このページの上へ